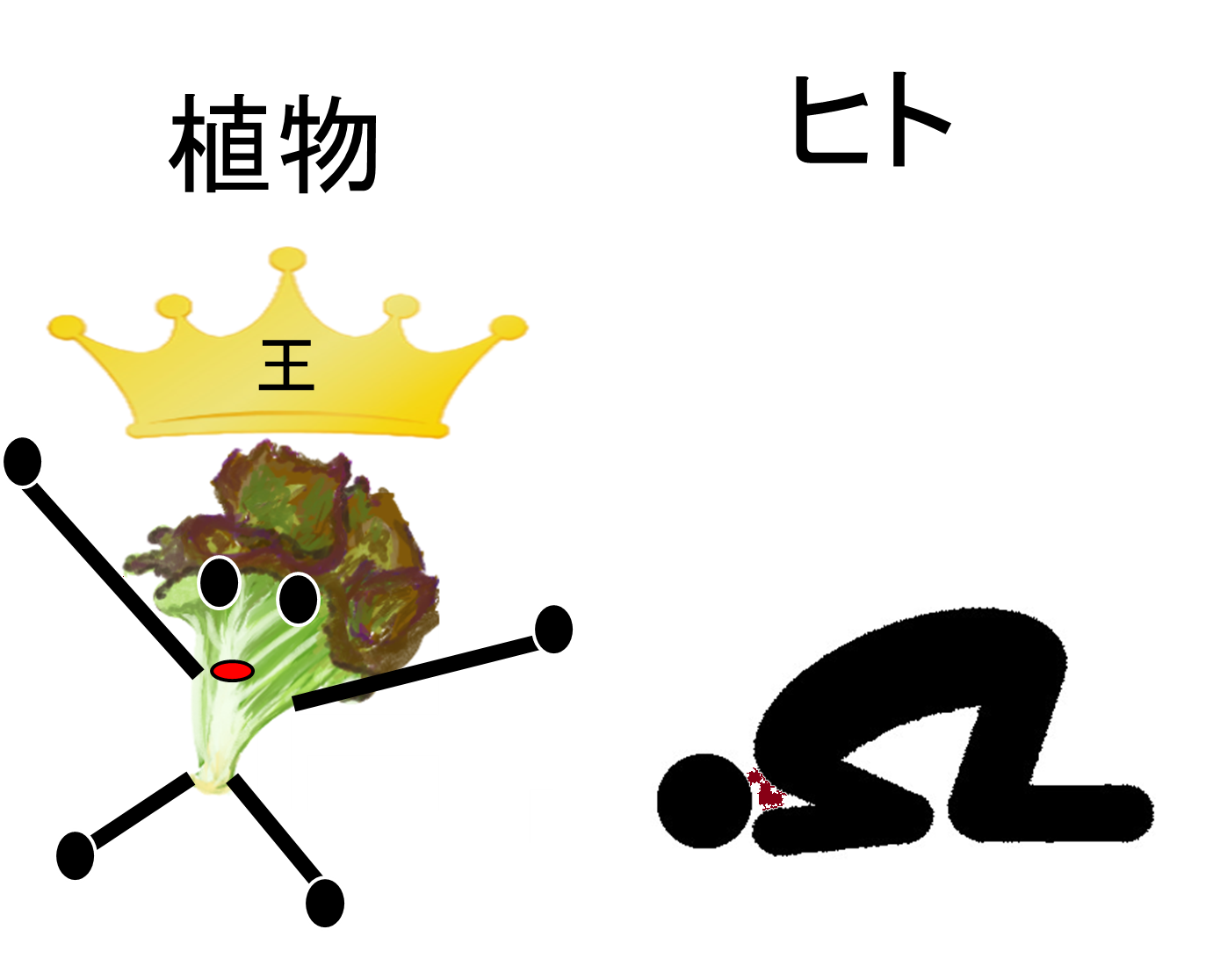生命の世界・・・生産者と消費者
我々動物は生きていくうえでご飯を食べる必要がある。例えばヒトは野菜や果物などの植物や豚や牛などのほかの動物を食べて身体の細胞を構成する。しかし世の中には何も食べていないのに体の細胞がどんどん増える生命がいる。!? それは・・・植物だ。植物は大気中の二酸化炭素と太陽光からデンプンを生み出し自身の茎や葉を成長させる。何も食べていないと言っても、空気も土の栄養も 食べているじゃないか!と反論が上がりそうだが、まさにその通りで、植物は空気と土(の中の無機塩類)を食べて生きている。まるで仙人。肉や野菜などの目に見える何かを食べている私たちにはとても神秘的に映る。他者を食べずとも自ら肉体を製造できる生命を、“生産者”と呼ぶ。一方、ヒトや動物が属するグループで、生産者が空気と太陽エネルギー(化学エネルギーを利用する生命もいる)から作り出した肉体を喰らい、自らの肉体とする者たちの総称を “消費者”と呼ぶ。
生産者ありきの消費者
前述の通り、消費者であるヒトは、生産者である植物を手に入れて我が物にしないと死んでしまう。それゆえ古代のヒトはヒエ・アワなどの穀物や木の実を採集し食した。え、ちょっと待って!植物が手に入らなくてもシカやイノシシの肉があるし“ノーぷろぶれむ!”なのでは!?実際ヒトは木の実だけでは腹が満たせないので他の消費者の肉も食べた。イノシシやシカ、魚、貝など様々な”非植物”を食べていた。しかしよく考えてみると、シカやイノシシは植物を食べないと大きくならないし死んでしまう。魚は小さな昆虫を食べるがその昆虫は草を食べて生きている。貝は水中の植物プランクトンを吸い込んで成長する。つまり、ほかの消費者を食する行為は“間接的に植物を体内に取り入れる行為”に他ならない。結論、やはり植物“様“がいなくなればヒトや動物は飢えて死に絶えてしまう。植物様はその土地の質、天候や自然災害などで沢山増えたり、全くいなくなったりする気分屋であるからヒトの生き死には植物様に握られていた。つまりヒトは植物の奴隷のようなもの(ちょっと言い過ぎかな)だったわけだ。ところがこの状況は”農業“の登場で一変する。
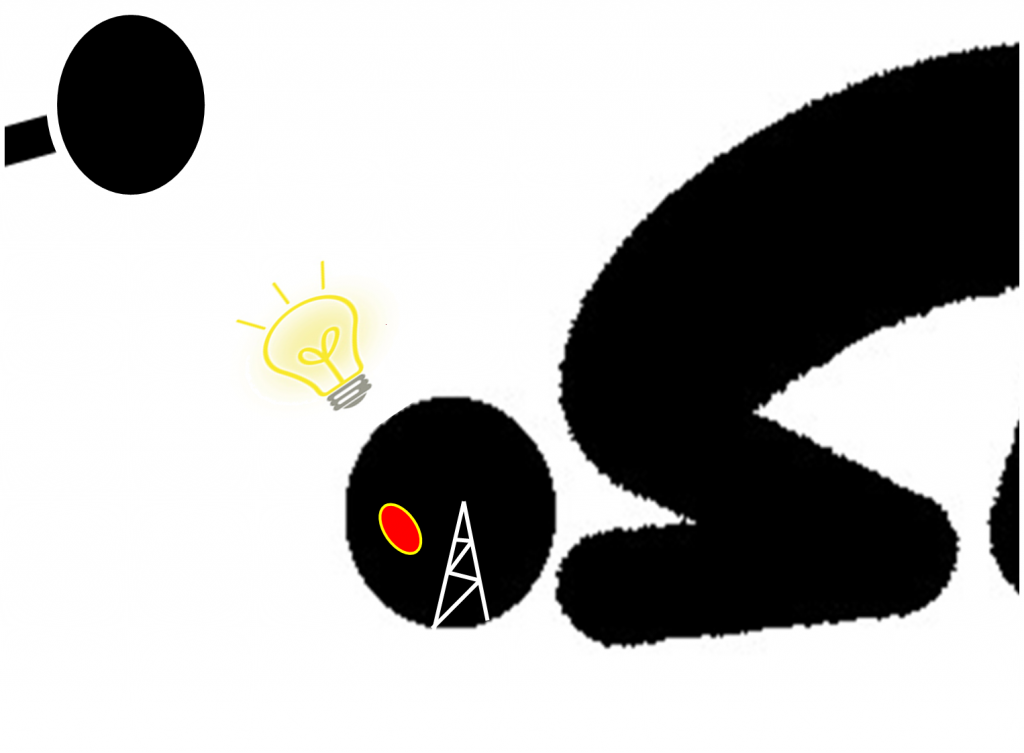
・・・続く!